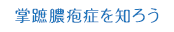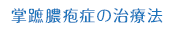病院に行く前に
※このサイトに示す画像および記事の無断転載を禁じます
治療費が高額になることはありますか?
治療法によっては高額になる場合があります。医療費が高額になった場合、患者さんの負担を軽減する国の制度があります。
医療機関の窓口で支払った医療費が、ある一定の金額(自己負担限度額※1)を超えると、差額が払い戻される「高額療養費制度」というものがあります。この制度は、全ての医療保険※2加入者が利用できます。原則として、自動的に払い戻されるわけではなく、自己負担額が高額になったときに、患者さんご自身が加入している医療保険に申請する必要があります。
なお、「限度額適用認定証」を受診時に病院の窓口に提示した場合、当月の窓口での支払いが自己負担限度額と同額になり、高額療養費の払い戻し手続きが不要になります。「限度額適用認定証」の交付も、患者さんご自身が加入している医療保険に申請することで交付されます。年齢・所得により手続きが異なります。70歳以上の方で現役並み所得(年収約1,160万円以上)の方と一般の方は、窓口で健康保険証と高齢受給者証を提示することにより、自己負担限度額となるため、「限度額適用認定証」の申請は不要です。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合(マイナ保険証)は、「限度額適用認定証」がなくても、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。
また、さらに負担を軽減できるしくみとして、同世帯で同じ医療保険に加入している方の医療費を合算できる「世帯合算」、過去12ヵ月以内に高額療養費の払い戻しが3回以上ある場合は4回目から自己負担限度額が下がる「多数回該当」があります。
(詳細は「高額療養費制度について」を参照)
※1 自己負担限度額は、年齢や所得により異なります。詳しくは、ご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。
※2 本項では、公的な医療保険[国民健康保険(国保)、健康保険(健保)、後期高齢者医療制度など]を、「医療保険」としています。
ご加入の医療保険によっては、さらに負担が軽減されることがあります。
医療保険によっては、高額療養費制度で設定されている「自己負担限度額」よりもさらに低い額を設定していることがあります(付加給付制度)。付加給付制度での上限額は、各医療保険が独自に設定していますので、患者さんご自身が加入している医療保険の窓口に問い合わせ、ご自身についての正確な情報を得ることが大切です。
支給申請には領収書が必要な場合があります。
「限度額適用認定証」等を受診時に病院の窓口に提示しなかった場合は、後日、加入している医療保険に高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあるため、領収書などは大切に保管しておきましょう。高額療養費の申請ができるのは、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。したがって、2年間はさかのぼって申請することができます。
詳細は厚生労働省のホームページ(「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)をご参照ください。